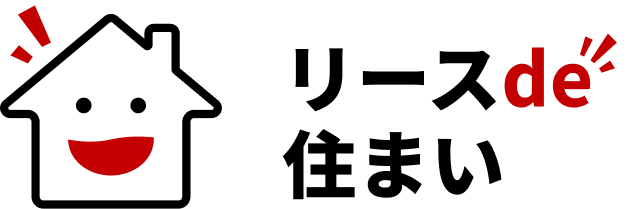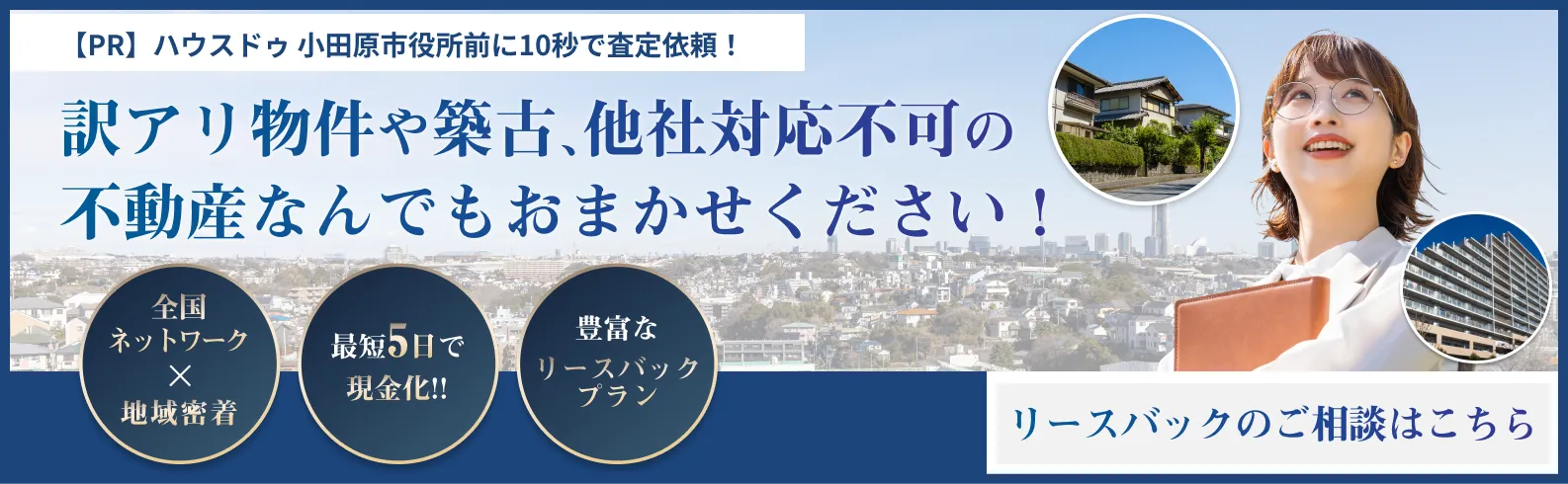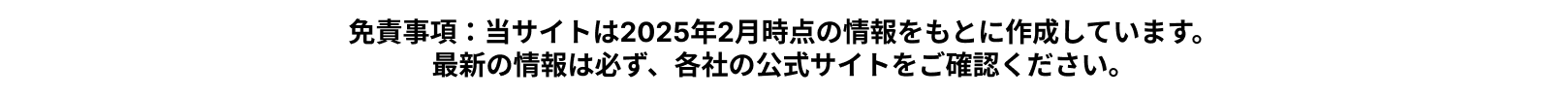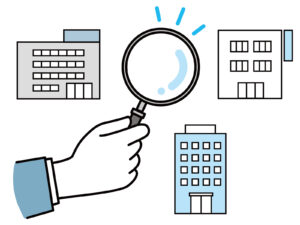自宅を売却した後も住み続けられるリースバックは、資金確保と生活の安定を両立できる手段として注目されています。不動産売却に伴い、リースバックを検討している方も多いでしょう。
しかし、売却益が発生する場合には税務上の手続きが発生し、確定申告が必要になる可能性があります。リースバックによって得た収入が課税対象となるかは、売却価格や取得費、各種控除など、さまざまな要素により異なります。
そこでこの記事では、リースバックで確定申告が必要となるケースや計算方法、手順、節税対策について解説していきます。リースバックを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
なお、以下では、西湘エリアでリースバックに対応しているおすすめの不動産会社をまとめているので、参考にしてください。
また、リースバックの基本的な仕組みやメリット、注意しておきたいトラブル事例までをまとめて知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
リースバックにおける確定申告が必要なケース3選

リースバックにおいて確定申告が必要になるケースは、以下の3つが挙げられます。
それぞれのケースについて解説していきます。
譲渡益(売却益)が発生した場合
リースバックで自宅を売却した際に譲渡益が発生した場合には、原則として確定申告が必要になります。
譲渡益とは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた残額で、この利益がある場合には「譲渡所得」として課税対象となります。取得費には物件の購入価格やリフォーム費用、譲渡費用には仲介手数料や登記費用などが該当します。
これらの金額が把握できていないと、課税額の算定が不正確になり、過少申告や追徴課税のリスクを伴います。また、譲渡益が出た場合でも、一定の条件を満たせば「3,000万円特別控除」などの特例を適用でき、課税額を軽減することも可能です。
とはいえ、これらの特例を活用するにも確定申告は不可欠であるため、必要書類の準備や申告内容の精査が求められます。
特例を適用する場合
譲渡所得に対して特例を適用する場合、確定申告が必要になる可能性があります。例えば「居住用財産の3,000万円特別控除」は、確定申告を通じて必要書類を税務署に届け出なければなりません。
申告を行わなければ、たとえ条件を満たしていても控除は適用されず、本来よりも多くの税負担が発生することになります。特例の申請には、譲渡契約書や住民票などの添付が求められます。
特例を適用することで税負担を大幅に軽減できますが、そのためには確定申告が不可欠です。
損失が出て繰越控除を希望する場合
リースバックによる不動産の売却額が譲渡損失となる場合でも、確定申告を行うことで、翌年以降の譲渡所得から控除できる「繰越控除」が適用できます。
繰越控除は最大3年間にわたり損失を控除できる制度で、将来に不動産や株式などを売却して利益が出た際に、その損失分を差し引くことが可能です。リースバックで課税される利益が発生していなくても、損失を資産として活用するには、確定申告が必要です。
確定申告を怠ると、損失の繰越が認められず、節税の機会を失ってしまいます。リースバックにより損失が出た場合でも、確定申告が必要になるケースがあるため注意しましょう。
確定申告が不要なケースとは?
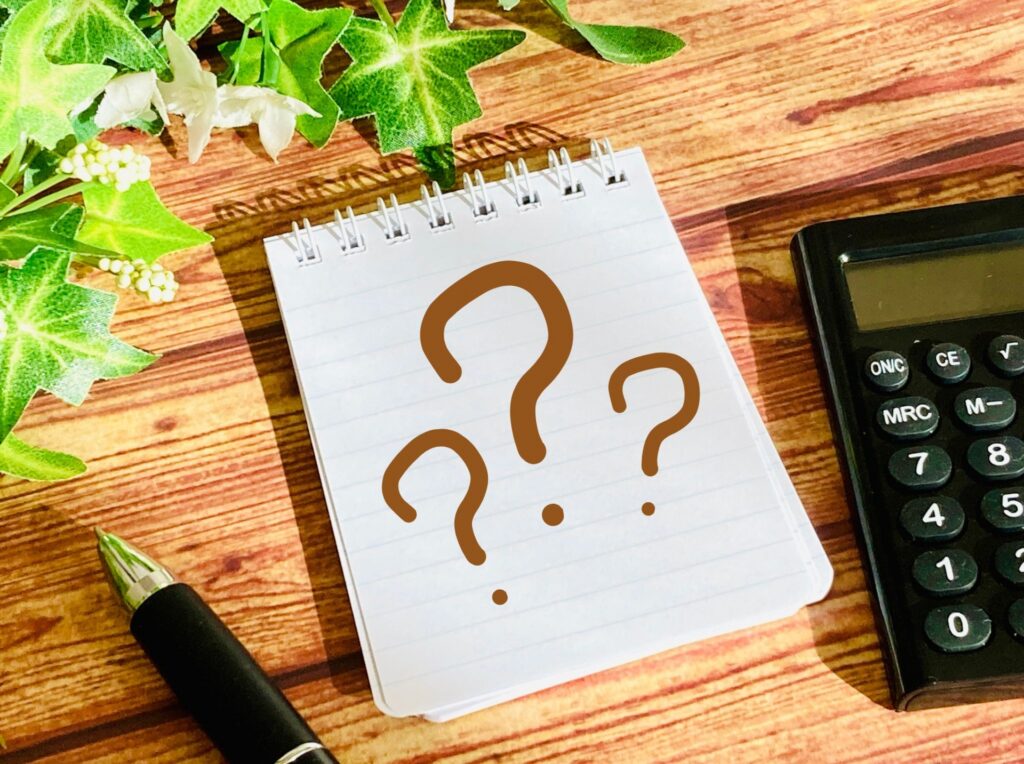
リースバックによる不動産売却でも、確定申告が不要になるケースがあります。
例えば「3,000万円特別控除」の適用が認められる場合は、確定申告が不要です。に譲渡所得から最大3,000万円が控除され、譲渡所得がゼロとなれば、課税対象がなくなり確定申告も不要になります。
ただし、確定申告が免除されるためには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。また、控除の適用が明確でない場合や、税務署からの確認が入る場合には、念のため確定申告を行うことが望ましいとされています。
このように、譲渡所得が発生しない、つまり損失以上となれば、確定申告は必要ありません。
リースバックで確定申告をしないとどうなる?
リースバックで不動産を売却した場合、譲渡所得が発生すると確定申告が必要です。確定申告を怠ったり誤った内容で提出すると、思わぬペナルティや不利益につながります。
ここでは、申告をしないことで起こり得る代表的な3つのリスクを解説します。
リスクを理解しておくことで、正しい手続きの重要性を実感できるはずです。以下で詳しく解説します。
無申告によるペナルティが発生する
譲渡益が発生しているのに確定申告をしなかった場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。税務署に指摘されてから申告した場合は、加算税の割合が高くなることもあるので注意が必要です。
申告をしないまま放置すると、税額だけでなく罰則的な負担が加わるため、経済的ダメージは大きくなります。したがって、リースバックによる売却も通常の不動産売却と同じ扱いとなるため、必ず期限内に申告を行うことが必要です。
過少申告の場合のリスク
申告はしたものの、売却益を過少に申告した場合もリスクがあります。税務署の調査で誤りが発覚すると、追徴課税として過少申告加算税が課される可能性もあるので注意が必要です。
さらに、意図的に少なく申告したとみなされれば重加算税の対象になる場合もあり、通常よりも大きな税負担となります。リースバックにおける売却価格や経費の計上は複雑になることがあるため、正確な計算と適切な記載が求められるでしょう。
還付を受けられない可能性がある
譲渡損失が出ている場合や特例を利用できる場合でも、確定申告をしなければ還付を受けることはできません。例えば、繰越控除や3,000万円特別控除などの制度は、申告手続きを行って初めて適用されます。
申告を怠ると、節税のチャンスを逃し、不要な税負担を抱えることにつながります。リースバックの取引でも、適切に申告することで税負担を軽減できるため、制度を活用する意識が重要です。
リースバックで生じる税金の種類と計算方法

リースバックで不動産を売却することで、以下の税金が発生します。
それぞれの税金と計算方法について解説していきます。
譲渡所得税
リースバックにおける譲渡所得税は、不動産売却によって得た利益に対して課される税金です。譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)特-別控除額
取得費には、購入代金や購入時の諸費用、リフォーム費用などが含まれます。譲渡費用には、売却時の仲介手数料や登記費用、測量費などが該当します。
計算された譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率が適用されます。これらは短期譲渡と長期譲渡に分けられ、それぞれの税率は以下の通りです。
| 譲渡所得の種類 | 所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%) |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) |
なお譲渡所得税は、売却した翌年の確定申告期間の2月16日から3月15日に申告・納付する必要があります。特別控除を適用する場合でも、確定申告は必要です。
固定資産税・都市計画税
リースバック後に発生する固定資産税と都市計画税の納税義務は、原則として買主に移転します。リースバック契約を締結し、所有権が移転した後は、売主である元所有者はこれらの税金を支払う必要がなくなります。
ただし、売却年の税金については、売主と買主の間で日割り計算による精算が行われるのが一般的です。売却日までの期間に対応する税額を売主が負担し、売却日以降の期間に対応する税額を買主が負担する形で調整されます。
固定資産税の計算方法は、以下の通りです。
固定資産税=課税標準額×標準税率1.4%
都市計画税については、以下の計算式で算出できます。
都市計画税=課税標準額×上限税率0.3%
固定資産税と都市計画税のどちらについても、住宅用地の場合、面積に応じて課税標準額が軽減されることがあります。
リースバック契約後はこれらの納税義務がなくなるため、固定資産税や都市計画税の負担から解放されることは、リースバックのメリットの1つと言えるでしょう。
印紙税
リースバックによる不動産売却では、売買契約書の作成時に印紙税が課されます。印紙税は、契約書に記載された金額に応じて定められた額の収入印紙を貼付し、消印することで納付します。印紙税の金額については、以下の通りです。
| 売却金額 | 印紙税額 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円超~50万円 | 400円 | 200円 |
| 50万円超~100万円 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超~500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円 | 60,000円 | 30,000円 |
令和9年3月31日までに作成される契約書については、表の右側の軽減税率が適用され、印紙税額が半額に減額されます。この軽減措置を受けるには、契約書に所定の収入印紙を貼付し、消印を行う必要があります。
登録免許税
リースバックにおいて登録免許税が発生するのは、将来的に不動産を買い戻す場合に限られます。売却時には買主が所有権移転登記を行うため、売主が登録免許税を負担することは通常ありません。
しかし、買い戻す際には再度所有権移転登記が必要となり、登録免許税の納付が求められます。登録免許税額は、固定資産税評価額を基に以下の税率で計算されます。
- 通常の税率:2%
- 土地の所有権移転登記:1.5%
- 抵当権設定登記:0.4%
確定申告に関するスケジュールと期限
リースバックによる売却で譲渡所得が発生した場合、確定申告を行う必要があります。その際に重要なのが申告や納税の期限を正しく理解しておくことです。期限を守らなければ延滞税や加算税といったペナルティが発生する可能性もあります。
ここでは、申告や還付のスケジュール、そして期限を過ぎたときの対応について解説します。
これらを把握しておくことで、余計なトラブルを避け、安心して手続きを進めることができます。以下で詳しく解説します。
申告書の提出期限と納税期限
確定申告書の提出期限は、原則として翌年の2月16日から3月15日までと定められています。また、納税についても同じ期限までに行う必要があり、期日を過ぎると延滞税や無申告加算税が課される可能性があるので注意が必要です。
また、リースバックによる売却益が発生した場合も、この一般的な確定申告のルールに従うことになります。税務署の混雑を避けるためにも、早めに書類を準備し、期限を意識したスケジュール管理を心がけることが重要です。
還付申告の期限(5年)
税金を払い過ぎている場合には、還付を受けるための申告が可能です。還付申告は通常の確定申告と異なり、翌年の1月1日から5年間提出することができます。
例えば、リースバックで損失が出て税金を納め過ぎた場合でも、この制度を活用すれば還付を受けられます。期限内であればいつでも申告可能なので、払い過ぎに気づいた時点で早めに手続きするのがおすすめです。
5年を過ぎると還付を受ける権利が失効するため、注意が必要です。
期限を過ぎた場合の対応方法
もし申告期限や納税期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに申告・納付を行うことでペナルティを最小限に抑えることが可能です。期限後に提出する申告は「期限後申告」と呼ばれ、延滞税や加算税が発生しますが、早めに対応するほど負担は軽くなります。
また、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告することで、加算税が軽減される制度もあります。リースバックによる売却で申告を忘れてしまった場合は、放置せず早急に対応することが重要です。
リースバック後の確定申告の手順
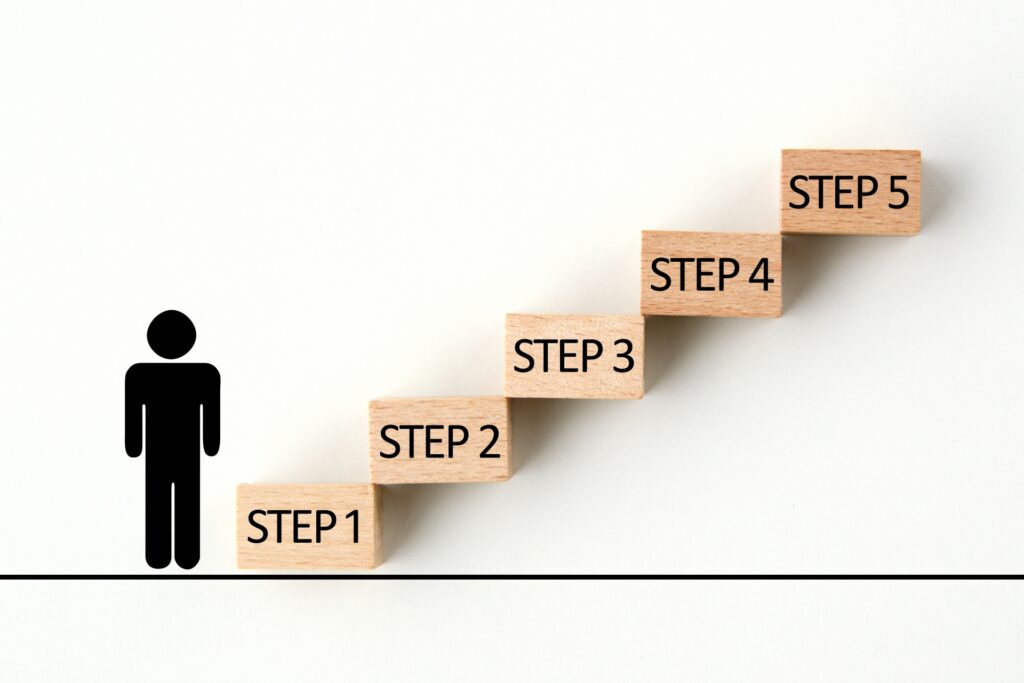
リースバック後に確定申告が必要になる場合、以下の手順で進めるのが基本です。
それぞれの手順について解説していきます。
必要書類の準備
リースバック後に確定申告を行うには、まず必要書類を準備します。主な書類としては、以下のようなものがあります。
- 売買契約書の写し
- 購入時の契約書および領収書
- 譲渡費用の領収書(仲介手数料、司法書士報酬、測量費など)
- 固定資産税評価証明書
- マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
- 住宅ローンの残高証明書
これらの書類は、譲渡所得の計算と特例の適用判断に不可欠で、税務署からの確認にも対応できるよう、原本を保管しておくようにしましょう。書類が不足している場合には、登記所や自治体から再発行を受ける必要があります。
譲渡所得の計算
必要書類を揃えたら、それらの書類を基に譲渡所得を計算します。
譲渡所得は確定申告書に記載するため、正確に計算しなければいけません。計算ミスをしないためには、不動産会社や税理士に相談し、チェックしてもらうことをおすすめします。
確定申告書の作成
譲渡所得の計算が完了したら、確定申告書を作成します。不動産の譲渡に関する申告には、以下の書類が必要です。
- 確定申告書B
- 分離課税用の申告書第三表
- 譲渡所得の内訳書
書類に記入ミスや漏れがあると、控除が適用されなかったり、税務署から確認が入る可能性があります。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を活用すれば、ガイドに従って入力するだけで書類が自動作成されるため、初めての方でも簡単に対応できます。
確定申告書を税務署へ提出
確定申告書の作成が完了したら、それらの書類を税務署への提出します。提出方法としては、以下の3つがあります。
- 管轄の税務署へ持参
- 郵送
- e-Taxを利用したオンライン提出
提出期限は通常、翌年の2月16日から3月15日までと定められており、期限を過ぎると延滞税や無申告加算税の対象となる場合があります。
書類を郵送する際には、控え用にコピーを同封し、返信用封筒を付けておくと、受領印付きの控えを返送してもらえます。e-Taxを利用すれば、自宅からの提出や納税も可能となり、添付書類の一部省略が認められるなどのメリットもあります。
リースバックによる譲渡所得がある場合、正確な提出が納税義務の履行につながるため、早めの準備と提出を心掛けましょう。
納税または還付手続き
確定申告書を税務署へ提出した後は、申告内容に基づいて納税または還付の手続きが行われます。譲渡所得に対して課税額が発生した場合は、原則として3月15日までに納付を完了させなければなりません。
納税方法には、以下のような方法を選択できます。
- 金融機関窓口
- 振替納税
- クレジットカード
- インターネットバンキング
一方、譲渡損失の発生や特別控除の適用により所得税が過払いとなっている場合は、還付申告となり、口座情報を記載することで1〜2か月程度で指定口座に還付されます。なお、還付金を早く受け取るには、e-Taxの利用がおすすめです。
リースバックで使える節税対策

リースバックにおいては、一定の条件を満たすことで以下の特例・控除が利用可能で、節税対策になります。
それぞれの特例・控除について解説していきます。
居住用財産の3,000万円特別控除
居住用財産の3,000万円特別控除は、マイホームを売却した際に発生する譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です適用条件を満たせば、大幅な節税が期待できます。適用の主な要件として、以下のようなものがあります。
- 売却物件が自己の居住用である
- 売却相手が親族や同族会社などの特別な関係者でない
- 過去2年間に同様の特例を利用していない
リースバックの場合でも、これらの条件を満たしていれば特別控除が適用可能です。ただし、形式的な売買と見なされないよう、実際に売却代金の授受が行われ、適正な売買契約と賃貸契約が締結されていることが重要です。
取得費加算の特例
取得費加算の特例は、相続税を支払った不動産を一定期間内に譲渡した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算し、譲渡所得税を軽減する制度です。
取得費に加算できる相続税額は、譲渡した財産に対応する部分に限られます。具体的には、相続税額に譲渡した財産の相続税評価額を掛け、全体の相続税評価額で除した金額が加算対象となります。
この特例を利用することで、譲渡所得が圧縮され、課税所得が減少します。ただし、他の特例との併用に制限がある場合があります。例えば、相続空き家の3,000万円特別控除とは併用できませんが、居住用財産の3,000万円特別控除とは併用可能です。
長期譲渡所得による軽減税率
所有期間が10年を超える場合、長期譲渡所得による軽減税率が適用されます。具体的には、以下の通りです。
| 譲渡所得額 | 税率 |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 14%(所得税10%、住民税4%) |
| 6,000万円を超える部分 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
軽減税率の適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 売却する不動産が居住用財産である
- 売却した年の1月1日時点でその不動産の所有期間が10年を超えている
- 譲渡先が親族などの特別な関係者でない
- 他の特例との併用がない
また、この軽減税率は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」との併用が可能です。
損益通算・繰越控除
リースバックで損失が発生した場合、確定申告を通じて「損益通算」や「繰越控除」を活用することで、将来の税負担を軽減できます。
損益通算とは、譲渡損失を他の所得と相殺することで、課税所得を減少させる制度です。たとえば給与所得がある場合、譲渡損失を差し引くことで所得税や住民税の負担を軽減できます。
一方、繰越控除は損益通算で相殺しきれなかった損失を翌年以降に繰り越し、最大3年間にわたり他の所得と相殺できる制度です。これにより、過去の損失を活用して課税所得を抑えることが可能となります。
これらの制度を適用するには、譲渡損失が発生した年に確定申告を行い、必要な書類を提出することが前提となります。申告を怠ると、繰越控除の適用が受けられなくなるため、注意が必要です。
確定申告時の注意点

確定申告を行う際には、以下の点に注意が必要です。
それぞれの注意点について解説していきます。
申告期限を厳守する
リースバックで不動産を売却した場合、確定申告は申告期限を厳守しなければいけません。
通常、確定申告の受付期間は翌年の2月16日から3月15日までと定められており、期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。たとえ納税額がゼロであっても、損益通算や繰越控除などの制度を利用するためには、期限内の申告が必須です。
また、確定申告に必要な書類の準備には時間がかかるため、余裕を持って手続きを進める必要があります。期限内の申告ができるように、なるべく早く準備を進めるようにしましょう。
必要書類は保管しておく
リースバックによる確定申告では、申告に使用した書類を一定期間保管しておく必要があります。売買契約書や取得費を証明する領収書、譲渡費用に関する明細などは、税務署から確認を求められることがあります。
その際に不備があると、控除が認められなかったり、申告内容に誤りがあると判断される可能性があります。原則として、確定申告書の提出から5年間は保管が推奨されており、紙のままだけでなく、スキャンしてデジタルデータとして保存することも認められています。
適切に管理しておくことで、不要なトラブルを未然に防ぐことにつながるでしょう。
特例が併用して適用できるか確認する
確定申告で特例を適用させる際は、併用できるかを事前に確認することが重要です。たとえば3,000万円特別控除は、取得費加算の特例との併用が認められています。一方で、居住用財産の買換え特例との併用は不可とされています。
また、損失が出た場合に適用できる損益通算・繰越控除も、他の特例との関係により適用可否が分かれます。
併用できない特例を同時に申請すると、税務署から修正を求められるリスクがあります。確定申告時には、どの特例が併用可能か、国税庁の資料や税理士の助言を参考に判断し、適切に記載するようにしましょう。
リースバックにおける確定申告が不安な方は不動産会社に相談しよう
リースバックで自宅を売却した場合、譲渡所得税の計算や特例の適用など、確定申告が必要になるケースがあります。
しかし「どんな書類を準備すればいいのか」「節税制度は利用できるのか」など、不安や疑問を抱く方も少なくありません。そんなときは、不動産会社に相談するのがおすすめです。
取引の流れや税制に詳しい担当者であれば、必要書類の確認や税理士の紹介など、適切なサポートを受けられます。専門家と連携している不動産会社を選べば、申告ミスを防ぎ、安心して手続きを進められるでしょう。
西湘でおすすめの不動産会社3選

最後に、西湘でおすすめのリースバックに対応した不動産会社3選を紹介します。
それぞれの会社について解説していきます。
ハウスドゥ 小田原市役所前

神奈川県小田原市荻窪に位置する「ハウスドゥ 小田原市役所前」は、リースバックに対応した地域密着型の不動産会社です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 屋号 | ハウスドゥ 小田原市役所前 |
| 会社名 | 株式会社Forest field |
| 所在地 | 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪531-6 |
| 電話番号 | 0465-34-2555 |
| リースバックページ | https://odawarashiyakusyomae-housedo.com/leaseback/ |
| 公式HP | https://odawarashiyakusyomae-housedo.com/sell/ |
| 免許番号 | 神奈川県知事(1)第31148号 |
住宅ローンの残債がある物件でも対応可能な「ハウス・リースバック」サービスを提供しており、売却後も賃貸契約を結ぶことで、住み慣れた自宅に居住し続けることが可能です。
また、最短5日での資金化に対応しており、急な資金需要にも対応できる点が特徴です。 将来的な買い戻しオプションを含めた契約条件の設定も可能で、顧客の多様なニーズに応えています。
ハウスドゥ 小田原市役所前 株式会社Forest fieldについて詳しく知りたい方は、こちらも合わせて御覧ください。
ハウスドゥ 小田原市役所前 株式会社Forest fieldについてさらに詳しく知りたい方は、公式HPでも確認できます。
センチュリー21住宅セレクション小田原店

センチュリー21住宅セレクション小田原店は、神奈川県小田原市成田に位置し、リースバックに対応した不動産会社です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 屋号 | センチュリー21 住宅セレクション小田原店 |
| 会社名 | 住宅セレクション株式会社 |
| 所在地 | 〒250-0862 神奈川県小田原市成田170-1 |
| 電話番号 | 0465-39-3250 |
| 公式HP | https://www.century21.jp/store/141203- |
| 免許番号 | 神奈川県知事(3)第28319号 |
全国展開するセンチュリー21のネットワークを活用し、迅速な売却活動を展開しています。特にリースバックにおいては、売却後も住み続けられるよう、顧客の生活設計や将来の資金計画を考慮した提案を行っています。
また、住宅ローンや資金計画に関する総合的なアドバイスも提供しており、安心して取引を進めることが可能です。店舗には経験豊富なスタッフが在籍し、顧客満足度の向上に努めています。
センチュリー21 住宅セレクション小田原店 住宅セレクション株式会社について詳しく知りたい方は、こちらも合わせて御覧ください。
ハートマイホーム小田原店
神奈川県西湘エリアでリースバックを検討されている方には、ハートマイホーム小田原店がおすすめです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 屋号 | ハートマイホーム小田原店 |
| 会社名 | 株式会社ダイトー建設不動産 |
| 所在地 | 〒250-0852 神奈川県小田原市栢山506-1 パストラル宮ノ上103 |
| 電話番号 | 0120-76-0338 |
| 公式HP | https://www.dyto.jp/baikyaku/ |
| 免許番号 | 神奈川県知事(5)24260号 |
ハートマイホーム小田原店は、不動産売却から注文住宅の建築までを一貫してサポートするワンストップ体制を整えており、顧客の手間を最小限に抑えています。
さらに、リースバックサービスにも対応しているのも特徴です。親身な対応と説明が評価されており、サービスの質も高く評価されています。
ハートマイホーム小田原店 株式会社ダイトー建設不動産について詳しく知りたい方は、こちらも併せて御覧ください。
まとめ
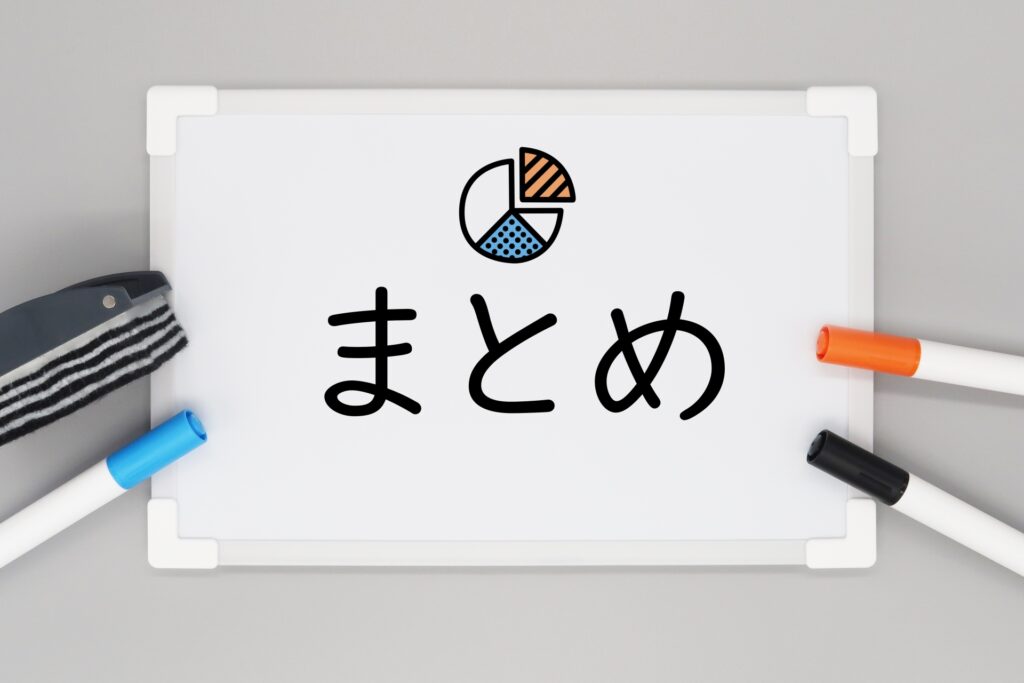
リースバックによる売却は、住み続けながら資金を確保できる有効な手段ですが、税務処理には注意が必要です。譲渡益が発生する場合は確定申告が必要となり、特例の適用可否や損益通算の活用なども検討する必要があります。
確定申告を行うには、必要書類の準備から譲渡所得の計算、申告書の作成・提出といった一連の流れを進めなければいけません。確定申告の基本的な流れを理解し、適用できる控除や特例を見極めることで、余計な税負担を避けられます。
リースバックを検討されている方は、不動産会社などの専門家に相談するのもおすすめです。期限内に確実に納税できるように、余裕を持って準備を進めましょう。